その6
コブタとコショー
少しの間アリスはその家をながめながら、次はどうしようかと考えていました。その時ふいにお仕着せ姿の召使が森から走り出てくると――(お仕着せ姿だったので召使だと思ったんです。そうでなければ顔だけ見てサカナと呼んでいたでしょう)――こぶしでコンコンッ!と音高く扉を叩きました。扉を開けて出てきたのは同じくお仕着せ姿の召使で、こちらは丸顔にカエルみたいな大きな目をしていました。見るとどちらの召使も髪粉をまぶしたくるくる巻きの毛で頭をおおっています。いったい何なんだろう、ととても興味が湧いたので、アリスは声を聞こうと森からちょっとだけ忍び出ました。
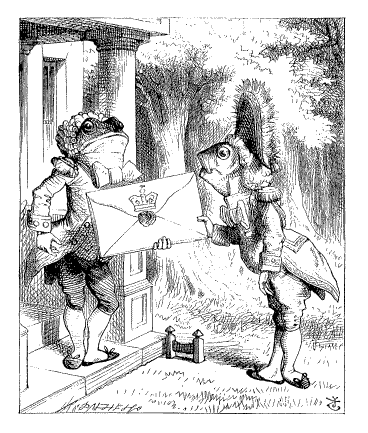
サカナ召使はまず脇に抱えていた特大の、ほとんど自分と同じぐらいの大きさの手紙を取り出しました。そしておごそかにこう言って、それをもう一人に手渡しました。「公爵夫人へ。女王様よりクロッケー・ゲームへのご招待。これにて確かに」カエル召使は同じくおごそかに、ただ言葉の順序をちょっと変えて復唱しました。「女王様より。公爵夫人へクロッケー・ゲームへのご招待。これにて確かに」
それから二人がそろって深々とおじぎをしたところ、くるくる巻きの毛がもつれ合ってしまいました。
アリスはこれを見て大笑いしてしまい、二人に聞こえないように森の中に駆け戻らなければなりませんでした。そして次にのぞいてみた時にはサカナ召使はいなくなっていて、もう一人は扉のそばの地面に座ってボーッと空を見上げていました。
アリスはおそるおそる扉まで近づいていって、ノックしました。
「ノックなさってもお役に立つようなことは何もございませんし、それには二つの理由がございます」と召使が言いました。「第一に、わたくしが扉に対しましてお嬢様と同じ側におります。第二に、中ではたいそうな音を立てていらっしゃるので、どなたにもお嬢様のノックがお聞こえになることはございません」そして確かに中ではとんでもなくやかましい音がし続けていました――ひっきりなしに泣きわめく声とくしゃみの音、さらに時々お皿やポットが粉々に砕けたような大音響です。
「すみません、それじゃあ、どうやって中に入ればいいんですか?」
「ノックなさるのにもいくらか意味があるかもしれませんが、もしもわたくしたちの間に扉があるのでしたら」召使はアリスに構わず先を続けました。「たとえば、もしもお嬢様が中におられるなら、ノックをなされば、わたくしがお出しして差し上げられますよねぇ」召使は話している間ずっと空を見上げていたので、これって絶対マナー違反よ、とアリスは思いました。「でも、どうしようもないのかも。このヒトの目って、もうほとんど頭のてっぺんに付いてるし。でも、とにかく聞いてることには答えてくれたっていいのに――どうやって中に入ればいいんですか?」アリスはもう一度繰り返しました。
「わたくしはここに座っております、明日まで――」
その時、扉が開くと、大きなお皿がシュッと飛び出て召使の顔に一直線。あわやその鼻をかすめると、後ろの木にぶつかって粉々に砕けました。
「――もしくはあさってまで、かもしれません」召使はまるでなんにもなかったように、同じ調子で続けました。
「どうやって中に入ればいいんですか?」アリスはまた、もっと大きな声でたずねました。
「そもそもお嬢様は中にお入りになるのですか? それがまず問題でございますよねぇ」
それは確かにそうです。ただ、アリスはそんなふうに言われたくはありませんでした。「ほんとにやんなっちゃう。みんながみんな、なんかかんか言い返してくるんだもん」とぶつぶつつぶやきます。「もう、いいかげんアタマに来ちゃう!」
召使はここが念の押しどころだと思ったようです。ちょっと言い換えて。「わたくしはここに座っております。離れては戻り、何日も何日も」
「でも、私はどうしたらいいの?」
「お気に召されるままに」そう言って召使は口笛を吹き始めました。
「もう、このヒトと話しても何にもなんない。まるっきりバカみたいなんだもん!」アリスは投げやりに言いました。そして結局、自分で扉を開けて中に入っていきました。
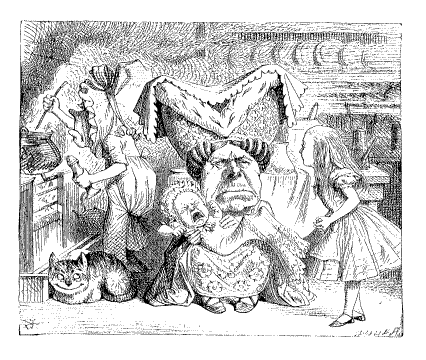
扉の向こうはすぐに広いキッチンになっていて、すみからすみまで煙がもうもうと立ちこめていました。公爵夫人が部屋のまんなかで三本脚の椅子に座って赤ちゃんをあやしています。そして
「絶対コショーがきき過ぎよ、あのスープ!」アリスはクシュンクシュンやりながら、どうにかこうにかつぶやきました。
確かにそこの空気はコショーがきき過ぎでした。公爵夫人でさえたまにハックションとやっています。そして赤ちゃんときたらクシャンクシャンとワーウワーウをひっきりなしに繰り返していました。そのキッチンでくしゃみをしていないのは二名だけ。コックと、それに大きな猫です。猫はかまどの前にうずくまって、ニターッと笑っていました。
「すみません、教えていただけますか? どうしてここの猫はあんなふうに笑ってるんですか?」アリスはちょっとおずおずと言いました。自分から先に話しかけるのが礼儀にかなっているのかどうか、あまり自信がなかったんです。
「あれはチェシャ猫です」と公爵夫人。「だからですよ。このブタ!」
最後はいきなり声を荒げたので、アリスはまさに跳び上がってしまいました。でも、赤ちゃんに言ったんだと、自分にじゃないとすぐに分かったので、勇気を出してまた話しかけました――
「チェシャ猫っていうのがいつも笑ってるなんて知りませんでした。と言うか、猫が笑えるなんて知らなかったです」
「猫は皆笑えます。それにたいていのはそうしますよ」
「私はそうする猫のことは知りませんけども」アリスはとても礼儀正しく言いました。会話になったのをかなり嬉しく思っていたんです。
「あなたはあまりものを知らないのです。それだけのことですよ」
この言われようはまるで気に入らなかったので、何か別の話にした方がいいな、と思いました。何にしようかと思っていると、コックがスープの大釜を火からおろすや、まわりの物を手当たりしだいに公爵夫人と赤ちゃんめがけて投げつけ始めました――火かき棒のたぐいがまず飛んできました。そのあと続いて鍋や小皿や大皿が雨あられです。公爵夫人はそれらが当たってもまったくお構いなし。それに赤ちゃんはもとからワーワー泣きわめいていたので、当たって痛がっているのかどうかは何とも言いようがありません。
「ねえ、お願い、気をつけてぇ!」アリスは怖くて怖くてぴょんぴょん飛び跳ねながら叫びました。「ああっ、赤ちゃんの大事なお鼻がなくなっちゃう!」とんでもなく大きな鍋が赤ちゃんの鼻をかすめて、あやうく持っていかれるところだったんです。
「皆が自分のことにだけ気をつけていれば、この世は今よりもずっと速やかに回りゆくでしょうに」公爵夫人はしゃがれ声でうなるように言いました。
「それはいいことじゃないですよ」アリスはものを知ってるところを少しは見せたかったので、もっけの幸いとばかりに言いました。「ちょっと考えてみてください、そしたら昼と夜がどんなことになっちゃうか! だって地球は一周するのに24時間ちょっきり――」
「ちょっきりと言えば」と公爵夫人。「この子の首をちょん切っておしまい!」
アリスはちらっとコックを見ました。今の言葉を真に受けたりしないかどうか、ちょっと心配だったんです。でも、せっせとスープをかきまぜていて、どうやら聞いてはいないようなので、また話を続けました。
「24時間、だと思うんですけど。それとも12時間でしたっけ? 確か――」
「あぁもう、わたくしをわずらわせないでちょうだい。数字は大の苦手なのよ!」そう言うと公爵夫人は再び我が子をあやし始めました。子守歌らしきものを歌いかけて、一節歌うたびに赤ちゃんをわさわさ揺さぶるんです――
|
「きびしくどなりつけなさい くしゃみをした子はたたくのよ くしゃみはただのいやがらせ わざとしているだけだもの」
コーラス (コックと赤ちゃんも一緒に)―― 「ワーウ! ワーウ! ワーウ!」 |
二番を歌っている間、公爵夫人はずっと赤ちゃんをぼんぼん放り上げていたので、かわいそうに、おチビちゃんの泣きわめく声と言ったら、アリスにはほとんど歌が聞き取れないほどでした――
|
「きびしくしかりとばします くしゃみをした子はたたきます ほんとはコショーがだいすきと ちゃんとわかっていますもの」
コーラス 「ワーウ! ワーウ! ワーウ!」 |
「ほら! あやしたければ少しぐらいは良くてよ!」公爵夫人はそう言って赤ちゃんをアリスに放りました。「わたくしは女王様とのクロッーケーの支度をしに行かなくてはならないの」とそそくさと部屋を出ていきます。コックがその背にフライパンを投げつけましたが、あわや、というところで当たりませんでした。
アリスは赤ちゃんを受け止めるのにちょっとばかり手こずりました。おかしな形をしたおチビちゃんで、手足をてんでの方向に伸ばしたからです。「まるでヒトデみたい」とアリスは思いました。かわいそうなおチビちゃんは受け止めた時には蒸気機関車みたいな鼻息を立てていて、しかも体をバタバタと曲げたり伸ばしたりし続けたので、とにかくはじめの1、2分は落っことさないでいるのが精一杯でした。
上手な抱き方が分かると(ねじり上げて結び目みたいにして、それからゆるまないように右の耳と左の足をギュッとつかんでおくんです)すぐにアリスは赤ちゃんを外に連れ出しました。「一緒に連れてかないと、きっと今日か明日にでもあの人たちにコロサレちゃう」とアリスは思いました。「置いてっちゃうのはヒトゴロシよね?」そう言うとおチビちゃんは返事にぶうぶうと鼻を鳴らしました(この時にはもうくしゃみはしていませんでした)。「お鼻を鳴らさないの。そんなのはちっともお行儀のいいお返事の仕方じゃないのよ」
赤ちゃんがまたぶうぶうと鼻を鳴らしたので、どうしたんだろうとアリスはとても不安になってその子の顔をのぞきこみました。鼻がすごく上を向いていて、人のよりもずうっとブタのに近いのは疑いようもありません。しかも目も赤ちゃんにしてはあまりにもちっちゃくなってきています。要するにその子の顔つきはまるで気に入りませんでした。「でも、すすり泣いてただけかも」そうも思ったので、涙は浮かんでるかな、とまた目をのぞきこみました。
ありません。一滴も浮かんではいません。「もし、ブタになるつもりだったらよ、ぼうや、もうあなたのことなんか知りませんからね。いい?」アリスは本気で言いました。かわいそうなおチビちゃんはまたすすり泣きました(か、鼻を鳴らしました。どちらとも言いきれません)。そしてしばらくはどちらも黙ったまま先に進みました。
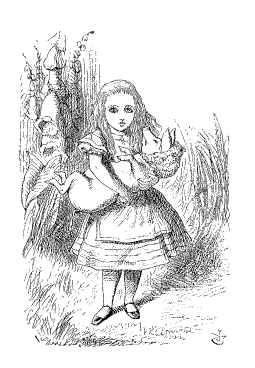 アリスが一人考え始めたばかりの時です。「さぁ、おうちに連れてったら、この子をどうすればいいのかな?」と、赤ちゃんがまたぶうぶうと鼻を鳴らしました。あんまり激しかったので、ちょっと不安になってその子の顔をのぞきこみました。今度は間違いようもありません。それはブタ以外の何者でもなく、アリスはそれ以上抱いているのがすっかり馬鹿馬鹿しくなってしまいました。
アリスが一人考え始めたばかりの時です。「さぁ、おうちに連れてったら、この子をどうすればいいのかな?」と、赤ちゃんがまたぶうぶうと鼻を鳴らしました。あんまり激しかったので、ちょっと不安になってその子の顔をのぞきこみました。今度は間違いようもありません。それはブタ以外の何者でもなく、アリスはそれ以上抱いているのがすっかり馬鹿馬鹿しくなってしまいました。
そこでおチビちゃんをおろしてやると、おとなしく森の中へチョコチョコと行ってしまったので、それを見て実にホッとした気分になりました。「もし、おっきくなってたら、おっそろしくブサイクな子になってたろうな。でも、けっこうハンサムなブタにはなるんじゃないかな」そう思ってアリスはブタとしてならとてもうまくやっていけそうな知り合いの子たちのことをあれこれと考え始めました。そしてちょうどこう思っていた時です。「あの子たちをそうするちゃんとしたやり方さえ分かってれば――」と、あのチェシャ猫が目に入ってちょっとドキッとしました。数メートル先の木の枝に乗っていたんです。

猫はアリスを見ると、ただニヤッと笑いました。気立てはいいみたい、とアリスは思いました。それでもすごく長い爪といっぱいの歯をしていたので、態度には気をつけた方が良さそうにも感じました。
「チェシャ、ニャンちゃん」アリスはいくぶんおっかなびっくり切り出しました。そう呼ばれるのを気に入るかどうか、まるで分からなかったからです。でも、猫はニマーッと笑っただけでした。「よし、ここまでは喜んでる」そう思って先を続けます。「お願いなんだけど、教えてもらえない? ここからどっちの方に行った方がいいか」
「そりゃあかなりのところ、お嬢ちゃんがどこに行きたいかによるな」と猫は言いました。
「どこでもそんなに構わないんだけど――」
「じゃあ、どっちに行っても構やしない」
「――どこかに行けるんだったらね」アリスはちゃんと伝えるために言い足しました。
「あ〜ぁ、必ず行けるさ、充分に長いこと歩きさえすりゃあ」
これには言い返せそうになかったので、アリスはほかのことを聞いてみました。「この辺にはどんな人たちが住んでるの?」
「あっちの方には」と猫は右の前足をくるくる回して、「帽子屋が住んでる。でもってあっちの方には」ともう一方の足を回して、「三月ウサギが住んでる。どっちでも好きな方に行きなよ。どっちもイカレてる」
「でも、イカレてるヒトたちのところなんか行きたくないわ」
「あ〜ぁ、そりゃあしょうがない。ここじゃみ〜んなイカレてるんだ。俺もイカレてる。お嬢ちゃんもイカレてる」
「どうして私がイカレてるなんて分かるの?」
「きっとそうさ。でなきゃここには来やしなかったろう」
それじゃ全然理由になってない、とアリスは思いました。でも、続けて言いました。「じゃあ、どうして自分がイカレてるって分かるの?」
「まずはじめに、犬はイカレちゃあいない。そいつはいい?」
「まぁ、そうね」
「ってことはだ、ほら、犬は怒るとうなるし、嬉しいとしっぽを振るだろ。ところが俺はだ、嬉しいとうなるし、怒るとしっぽを振る。ゆえに、俺はイカレてる」
「私はそれ、のどを鳴らすって言うわ、うなるじゃなくて」
「好きに言やあいい。今日、女王様とクロッケーするの?」
「ぜひしたいけど、まだ招待されてないの」
「そこで会えるさ」そう言うと猫は消えてしまいました。
これにはさほど驚きませんでした。おかしなことが起こるのにはいいかげん慣れっこになってきていたんです。猫はアリスがまだそちらを見ているうちに、いきなりまた現れました。
「ところでさ、赤ちゃんはどうなった? もうちょっとで聞くのを忘れるとこだった」と猫は言いました。
「ブタになっちゃったわ」アリスは落ち着き払って答えました。まるで猫がごく普通に戻ってきたみたいです。
「だろうと思った」そう言うと猫はまた消えてしまいました。
また出てくるんじゃないかな、とアリスはちょっと待ちました。でも、猫は現れなかったので、少ししたあと三月ウサギが住んでいると言われた方へ歩いていきました。「帽子屋さんは前にも何度か見たし、三月ウサギって何よりもずうっと面白そうだし、もしかしたら、今は5月だから、めちゃくちゃイカレたりはしてないかも」と思います。「悪くても3月ほどイカレてないわ」そう言って上を見ると、猫がまた木の枝に乗っていました。
「『ブタ』って言ったっけ、それとも『ムダ』だっけ?」と猫は言いました。
「『ブタ』って言ったの。それとそんなにいきなり出たり消えたり、もうしないでほしいんだけど。なんだかクラクラしちゃうわ!」
「いいとも」猫はそう言うと、今度はかなりゆっくりと消えていきました。しっぽの先から消え始め、おしまいはニヤニヤ笑いです。ニヤニヤ笑いは猫がすっかり消えたあともしばらく残っていました。

「うわあ! 笑いの浮かんでない猫がいるのはよく見るけど、猫のいない笑いが浮かんでるなんて! こんなにおかしなもの、生まれてはじめて見た!」とアリスは思いました。
さほど遠くに行くまでもなく、三月ウサギの家が見えてきました。その家がきっとそうだと思ったのは、煙突が二本、耳みたいな形をしていたし、屋根が毛皮で葺いてあったからです。とても大きな家だったので、このまま近づくのは嫌だな、と左手側のキノコをまた少しかじって、背たけを60センチぐらいに伸ばしました。それでも向かっていくのはいくぶんおっかなびっくりで、心の中ではこう思っていました。「もし、やっぱりめちゃくちゃイカレてたら! こっちじゃなくて帽子屋さんに会いに行けば良かった!」