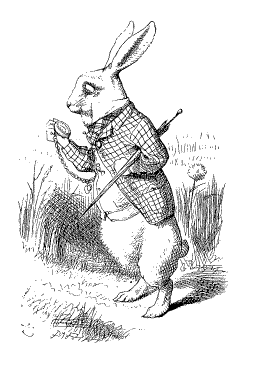
その1
アリスは川辺でお姉さんのそばに座っていることに、かなりうんざりしてきていました。何もすることがないってことにも。一、二度お姉さんの読んでいる本をのぞいてみたりもしたんですが、さし絵も会話もなかったので、「でも、本が何の役に立つの? 絵もセリフもなくて」と思ったものでした。
ですからじっくりと考えていたんです(できるだけですが。その日は暑くてとっても眠かったし、頭もぼうっとしていたので)、ヒナギクで花飾りを作るのは、わざわざ立ち上がってヒナギクを摘むほど楽しいことかどうか。とその時ふいに、赤い目の白ウサギが一匹、すぐそばを駆けていきました。
そのこと自体はそんなにめずらしくはありません。でも、そのウサギが「あ〜まずい! まずいよ! えらいこと遅れちまう!」とひとりごとを言うのが聞こえても、アリスはそんなに変だとは思いませんでした(あとになってよく考えてみた時には、あれで驚かなくちゃいけなかったんだ、って気がついたんですが、その時はそれがみんなごく普通のことみたいに思えたんです)。それでもそのウサギがなんとチョッキのポケットから時計を取り出して、それを見て、それからまた駆けていった時には、思わずパッと立ち上がりました。チョッキにポケットがあるとか、そこから取り出した時計を持っているとか、そんなウサギはこれまで見たことない、と頭にひらめいたんです。そしてもう興味いっぱい、夢中になってウサギを追いかけて野原を走っていき、ウサギが生け垣の根元の大きなウサギ穴にピョンッ、と飛びこむところをぎりぎり目にすることができました。
次の瞬間にはウサギを追って穴にもぐりこんでいました。いったいどうやってまた出てくるかなんて、まるで考えもしませんでした。
ウサギ穴はしばらくはトンネルみたいにまっすぐ伸びていましたが、そのあといきなりガクンと落ちこんでいました。あんまり急だったので、止まろうと思う間もなく、気がついた時には深い深い井戸のような穴を落ちていました。
穴がすごく深かったか、落ちるのがすごくゆっくりだったか、そのどちらかでした。なにしろ落ちながらまわりを見回したり、次はどうなるんだろうと考えたりする時間がたっぷりとあったんです。まず、どんなところに向かっているのかと下を見てみましたが、暗くて何も見えません。次にまわりを見て、壁が食器棚や本棚でいっぱいなのに気がつきました。あっちこっちに地図や絵が釘にかかっているのも見えます。アリスは棚の一つを通り過ぎる時、つぼを一つ取りおろしました。「オレンジ・マーマレード」とラベルがはってあったんです。でも、本当にがっかり、中はからっぽでした。アリスはつぼを落としたくなかったので(下にいる誰かをコロシちゃうかも、と思ったんです)、食器棚の一つを通り過ぎる時、なんとかその中におさめておきました。
「よぉし! こんなに落ちたんだもん、もう階段をころがり落ちたって平気よ!」とアリスは思いました。「なんて強い子だって、うちじゃみんなが思うわ! もちろん私はなんにも言わないもの。たとえおうちのてっぺんから落ちたって!」(それはたぶん、ほんとでしょう)
どん、どん、下へ。このままずうっと落ち続けるんでしょうか?「これまでに何キロ落ちたのかな?」とアリスは口にしました。「きっと地球のまんなかあたりに着くとこよ。えっとぉ、そうすると6000キロになるんじゃないかな――」(これはね、こういったことをいろいろと学校で教わったので、今は知識を披露するにはあんまりいい機会じゃありませんけれど、なにしろ聞いている人が一人もいませんから、それでも口に出して繰り返すのはいいおさらいだったんです)「――そう、それがだいたい正しい距離よ――でも、イ度やケイ度は何度まで来たのかな?」(緯度も経度もどういうものかさっぱり分からなかったんですが、口にするのには聞こえのいい、立派な言葉だと思ったんです)
少しするとまたひとりごとを言い始めました。「地球を突き抜けちゃうんじゃないかな! すごくおかしな感じ、頭を下にして歩く人たちの中に出てくなんて! タイヤキ人、だったと思うけど――」(聞いている人が一人もいないことに、この時はむしろホッとしました。ちっとも正しい言葉には思えなかったので)「――でも、そこが何て名前の国か聞かなくちゃね。すみません、おばさま、ここはニュージーランドですか、それともオーストラリアでしょうか?」(そしてそう言いながらていねいにおじぎをしようとしました――考えてみてください、空中を落ちながら、片足を引いて、ひざを曲げて、スカートをつまんでおじぎをするんですよ! あなただったらやってのけられると思います?)「でも、そんなこと聞いたら、なんてものを知らない子だって思われちゃう! 駄目、聞くなんてダメ。もしかしたらどこかにちゃんと書いてあるかもしれない」
まだ、まだ、下へ。 ほかには何もすることがないので、アリスはすぐにまたおしゃべりを始めました。「ダイナが今夜はとってもさみしがるだろうな!」(ダイナというのは猫です)「みんながあの子のティータイムのミルクを覚えててくれるといいんだけど。あぁ、ダイナ! 一緒にここにいてくれたらなぁ! 空中にはネズミはいないけど、でも、コウモリをつかまえるかも。あれってネズミにそっくりだしね。でも、猫はコウモリを食べるのかな?」 そしてここでかなり眠たくなってきて、夢見心地でつぶやき続けました。「猫はコウモリを食べる? 猫はコウモリを食べる?」そして時々、「猫をコウモリは食べる?」これはね、どっちにも答えられなかったので、どっちでもたいした問題じゃなかったんです。アリスは自分が寝込んでいるのを感じました。そして夢を見始めたばかりの時です。夢ではダイナと手をつないで散歩をしながら、とても真剣にダイナに話しかけていました。「いい、ダイナ。本当のことを教えて。コウモリを食べたことはある?」と、いきなりドサン!バサッ!と小枝と枯れ葉の山の上に落っこちて、落ちるのは終わりになりました。
アリスはケガ一つなく、すぐにパッと立ち上がりました。上を見てみましたが、頭上は一面真っ暗です。前を見るとまた別の長い通路が伸びていて、あの白ウサギの姿がまだそこにありました。奥に向かって急いでいます。ぐずぐずしてはいられません。風のようにアリスは走り、ウサギが角を曲がりながらこう言うのをぎりぎり耳にすることができました。「あぁ、ミミ様おヒゲ様、こんなに遅れちまうとは!」そのすぐあとに角を曲がりましたが、ウサギはもうどこにも見あたりません。気がつくとそこは細長い、天井の低い
ホールにはずらっと扉が並んでいましたが、どれもみんなカギがかかっていました。ですから片側をずーっと向こうに、反対側をずーっとこちらにと、扉をみんなためしながら一周してきてしまうと、ホールの真ん中をとぼとぼと歩いていきながら、いったいどうしたら出てけるのかなぁ、と思っていました。
ふいに小さな三本脚のテーブルに行き当りました。全体がガラスでできています。テーブルの上にはとても小さな金色のカギが一個載っているだけで、まず思ったのは、このホールの扉の鍵かも、ということでした。でも、残念! カギ穴が大きすぎるか、カギが小さすぎるかですが、とにかくどの扉もどうしても開けられません。ところが二回り目のこと。それまで気がつかなかった背の低いカーテンにぱったり行き会って、それをめくってみたところ、高さ40センチぐらいの小さな扉がありました。そのカギ穴に小さな金色のカギをためしてみると、なんとも嬉しいことに、これがぴったり!
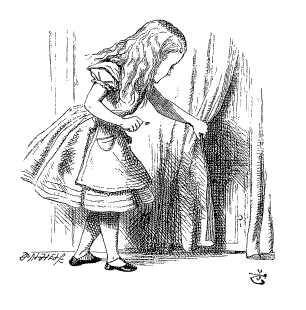 扉を開けると、中はせまい通路に続いていました。ネズミ穴よりそう広くもありません。ひざまずいてのぞいてみると、通路の先にこれまで誰も見たことのないほど美しい庭園が見えました。どんなにこの薄暗いホールを抜け出したいと、そして色あざやかな花壇や涼しげな噴水たちの間を歩き回りたいと願ったことでしょう。でも、戸口に頭をくぐらせることさえできません。「でも、頭がくぐってくれたって、カタナシじゃほとんど役には立たないな」とかわいそうにもアリスは思いました。「あぁ、ほんとに望遠鏡みたいに体が縮まればいいのに! なんとかなると思うんだけどな、とっかかりさえ分かれば」これはね、ここのところあんまりおかしなことばかり起こっているので、本当に無理なことなんてほとんどないような気がしてきていたんです。
扉を開けると、中はせまい通路に続いていました。ネズミ穴よりそう広くもありません。ひざまずいてのぞいてみると、通路の先にこれまで誰も見たことのないほど美しい庭園が見えました。どんなにこの薄暗いホールを抜け出したいと、そして色あざやかな花壇や涼しげな噴水たちの間を歩き回りたいと願ったことでしょう。でも、戸口に頭をくぐらせることさえできません。「でも、頭がくぐってくれたって、カタナシじゃほとんど役には立たないな」とかわいそうにもアリスは思いました。「あぁ、ほんとに望遠鏡みたいに体が縮まればいいのに! なんとかなると思うんだけどな、とっかかりさえ分かれば」これはね、ここのところあんまりおかしなことばかり起こっているので、本当に無理なことなんてほとんどないような気がしてきていたんです。
その扉のそばで待っていてもしかたがなさそうだったので、アリスはテーブルのところに戻りました。戻ってみたら別のカギがあるかも、じゃなかったら少なくとも人を望遠鏡みたいに縮める手順を書いた本が、と多少期待もしていました。今度はテーブルの上に小さなびんがありました(「前には絶対ここにはなかった」とアリスは言いました)。びんの首には紙のラベルがくくりつけられていて、ラベルには「飲んで」と大きな字で美しく印刷してありました。
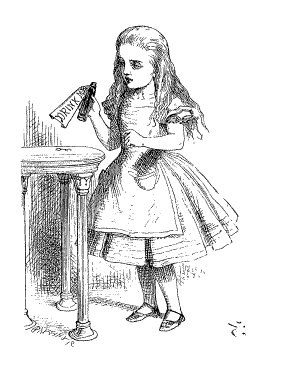 「飲んで」とあるのはいいんですが、小さいながらもかしこいアリスはそんなことをおいそれとするつもりはありませんでした。「駄目、まず調べるの。そして『毒』って書いてないかどうか確かめるの」と言いました。アリスは子供のための良いお話をいくつか読んだことがあって、そのお話では子供たちがやけどをしたり、けものに食べられてしまったり、そのほかの嫌な目に会ったりするんですが、それはみんな子供たちが親しい人の教えてくれた簡単な決まりごとをいつも忘れてしまうせいなので、たとえば真っ赤に焼けた火かき棒は長いこと持ちすぎるとやけどをします、とか、ナイフで指をうんと深く切ると、たいてい血が出ます、といったようなことですが、「毒」と書いてあるびんの中身をたくさん飲むと、遅かれ早かれまず間違いなく体をこわします、というのを一度も忘れたことがなかったんです。
「飲んで」とあるのはいいんですが、小さいながらもかしこいアリスはそんなことをおいそれとするつもりはありませんでした。「駄目、まず調べるの。そして『毒』って書いてないかどうか確かめるの」と言いました。アリスは子供のための良いお話をいくつか読んだことがあって、そのお話では子供たちがやけどをしたり、けものに食べられてしまったり、そのほかの嫌な目に会ったりするんですが、それはみんな子供たちが親しい人の教えてくれた簡単な決まりごとをいつも忘れてしまうせいなので、たとえば真っ赤に焼けた火かき棒は長いこと持ちすぎるとやけどをします、とか、ナイフで指をうんと深く切ると、たいてい血が出ます、といったようなことですが、「毒」と書いてあるびんの中身をたくさん飲むと、遅かれ早かれまず間違いなく体をこわします、というのを一度も忘れたことがなかったんです。
でも、このびんには「毒」と書いてはありませんでした。そこで思いきって味見をしてみると、これがとってもおいしかったので(もっとはっきり言うと、チェリーパイと、カスタードと、パイナップルと、七面鳥の丸焼きと、キャラメルと、ほかほかのバタートーストをミックスしたみたいな味でした)、たちまちすっかり飲みほしてしまいました。
|
|
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
「すっごくおかしな感じ! きっと望遠鏡みたいに縮んでるんだ!」とアリスは言いました。
そして本当にその通りでした。背たけは今やたったの25センチです。そしてこの大きさならあの小さな扉を通って素敵なお庭に行くのにぴったりだ、と顔を輝かせました。それでもまずはもう縮まないかどうか確かめようとしばらく待ちました。これにはちょっぴり不安だったんです。「だっておしまいにはよ、ローソクみたいにすっかり消えちゃうかも。そしたら私、どんなふうになっちゃうのかな?」そう思ってローソクの炎はローソクが吹き消されたあと、どんなふうになるのか思い描いてみようとしました。これまでにそんなものを見た覚えなんてありませんから。
しばらくしたあと、それ以上何も起こらなかったので、今すぐあのお庭に行こうと決めました。ところが、あぁ、かわいそうなアリス! 扉までやってきた時、あの小さな金色のカギを忘れてきてしまったのに気がつきました。そしてそれを取りにテーブルまで戻った時、そのカギにはとても手なんか届かないと気がついたんです。ガラス越しに実にはっきりとカギが見えていたので、いっしょうけんめいテーブルの脚の一本をよじ登ろうとしましたが、これがすべることすべること。そしてそうしているうちにすっかりくたびれてしまい、かわいそうに、この小さな子は座りこんで泣き出してしまったんです。
「ほら、そんなふうに泣いてたってしょうがないでしょ!」アリスは自分に向かってちょっときつく言いました。「いい、今すぐ泣くのをやめるの!」アリスはたいてい自分に向かってとてもいい意見を言いますし(もっともまずその通りにはしませんが)、時には目に涙が浮かぶほどきびしく自分をしかったりもするんです。それに一度、自分対自分のクロッケーのゲームで、自分をだましたということで、自分のほおをひっぱたこうとした覚えもあります。このユニークな子は二人ごっこが大好きだったんです。「でも、二人ごっこなんて今は何の役にも立たない!」とかわいそうにも思いました。「だって私、一人分もまともに残ってないんだもの!」
ほどなくテーブルの下にあった小さなガラスの箱に目がとまりました。箱を開けてみると中にはとても小さなケーキが入っていて、ケーキの上には「タベテ」とほしぶどうでみごとにしるしてありました。「よし、食べちゃお」とアリスは言いました。「それでおっきくなったらカギに手が届くし、ちっちゃくなったら扉の下をはってけるし。だからどっちにしてもあのお庭に行けるんだから、どっちになってもかまわないわ!」
アリスはほんの一口食べてみて、どっちになるのか確かめようと頭のてっぺんに手を当てながら、「どっち? どっち?」と不安げに心の中でつぶやきました。でも、同じ大きさのままだったのでちょっと驚いてしまいました。もちろん普通ケーキを食べた時はそういうものです。でも、おかしなことが起こる方が当たり前のような感じになっていたので、普通のことしか起こらないなんて、そんな毎日はひどく退屈でつまらなく思えてしまいました。
そんなわけでケーキに取りかかると、あっという間に片づけてしまいました。
|
|
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|