誰がパイを盗んだの?
ハートの王様と女王様はアリスたちがやってきた時には玉座に着いていて、まわりには大群衆が集まっていました――トランプ一組全員はもちろん、ありとあらゆる小鳥や小さな動物たちが。召使のジャックが鎖につながれてみんなの前に立っていて、左右にはそれぞれ一人ずつ見張りの兵士が付いています。そして王様のそばには白ウサギがいて、片手にラッパを、もう片方の手には羊皮紙の巻物をたずさえていました。法廷のちょうどまんなかにはテーブルがあって、パイの盛られた大皿が載っています。すごくおいしそうだったので、アリスはそれを見ておなかがぺこぺこになってしまいました――「裁判を済ませて、あのおやつを配ってくれないかなぁ!」と思いましたが、そうはなりそうになかったので、暇つぶしにまわりのものを一渡り見ていきました。
裁判所に入ったことはこれまで一度もありませんが、本で読んだことはあったので、そこにあるものはだいたいみんな名前が分かって、結構いい気分でした。「あれが裁判官。かつらが立派だもの」アリスは心の中でつぶやきました。
ちなみにその裁判官は王様でした。でも、かつらの上に冠を載せていたので(どんなふうにしたのか確かめたければ、口絵を見てください)、まるでしっくりきているようには見えませんでしたし、もちろん似合ってもいませんでした。
「で、あそこが陪審員席で、あの十二匹の生き物(「生き物」って呼ぶしかなかったんです。何しろ獣もいれば、鳥もいましたから)、あれが陪審員てことね」アリスはちょっと得意になって、陪審員という言葉を二、三度心の中で繰り返しました。自分ぐらいの子でともかくも意味を知ってる女の子なんてそうはいないと思ったんです。確かにその通り。もっとも「裁判員」でもちゃんと用は足りたでしょうけど。
十二匹の陪審員はみんなひどくせわしげに石板に何か書いていました。「あれは何をしてるの?」アリスはグリフォンにひそひそ声で言いました。「まだ書きとめることなんて何もないはずだけど、裁判も始まってないのに」
「自分の名前を書きとめてんだよ」グリフォンもひそひそ声で答えました。「裁判が終わる前に忘れちまうといけねえからな」
「バッカみたい!」アリスは腹が立ってつい大声を上げ、でも、あわてて口をつぐみました。「法廷では静粛に!」と白ウサギが叫んだんです。そして王様もめがねをかけて、誰がしゃべっているのかと、きょろきょろと法廷を見回しました。
アリスにはまるで肩越しにのぞいているみたいによく見えましたが、陪審員全員が「馬鹿みたい!」と石板に書きとめていました。おまけにそのうちの一匹が「馬鹿」という字が書けなかったことや、教えてくれるよう隣の者に頼まなければならなかったことまで分かりました。「裁判が終わる前に石板はごっちゃごちゃになっちゃうな!」とアリスは思いました。
陪審員の一匹がキーキーきしる石筆を持っていました。これにはもちろんアリスはとても我慢ができなかったので、法廷をぐるっと回ってその後ろに行くと、たちまち隙を見てパッとその石筆を取り上げてしまいました。あんまり素早くやったので、かわいそうに、その小さな陪審員(トカゲのビルでした)には石筆がどうなったのかさっぱり分かりません。ですからそこら中を探し回ったあげく、その日はもうずっと一本の指で書かなければならなくなりました。でも、これはほとんど役には立ちませんでした。指では石板に跡なんか何も残りませんから。
「伝令官、起訴状を読み上げよ!」と王様が言いました。
これを受けて白ウサギはラッパを三回吹き鳴らし、それから羊皮紙の巻物を広げると、次のように読み上げました――
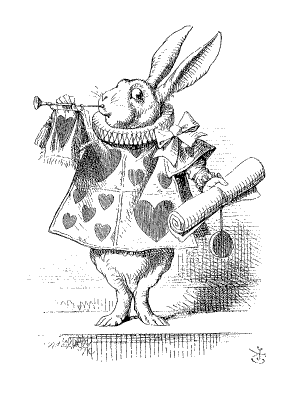
|
「ハートの女王様 パイをつくった 一日かかって パイをつくった めしつかいがこっそり パイをぬすんだ 一つものこさず パイをぬすんだ」 |
「評決を取りまとめよ」王様が陪審団に言いました。
「まだです、まだです!」あわててウサギがさえぎりました。「その前にすることがたくさんございます!」
「第一の証人を召喚せよ」あらためて王様が言い、白ウサギはまたラッパを三回吹き鳴らすと、大声で呼びました。「第一の証人!」
第一の証人は帽子屋でした。片手にティーカップ、もう片方の手にバタつきパンを一切れ持って入廷してきました。「お許し下さい陛下、このようなものを持ちこみまして。ただ、お呼び出しを受けました時、まだお茶を済ませておりませんでしたので」
「済ませておくべきじゃったぞ。いつ始めたのじゃ?」と王様。
帽子屋は三月ウサギに目をやりました。帽子屋のあとについて、ヤマネと腕を組んで法廷に入ってきていたんです。「3月の14日であった、と思いますが」
「15日だ」と三月ウサギ。
「16日」とヤマネ。
「合わせて書きとめよ」王様が陪審団に言いました。すると陪審団は日付を三つともせっせと石板に書きこんで、それから三つを足し合わせると、しめていくらと書きとめました。
「そちのその、帽子をとれ」王様が帽子屋に言いました。
「これはあっしのではございませんで」
「盗みおったのじゃ!」王様は声を上げて陪審団に向き直り、陪審団はただちにその犯行を記録しました。
「帽子は売り物でございます。あっし自身のは一つもございません。あっしは帽子屋ですので」帽子屋は弁明を加えました。
ここで女王様がめがねをかけると、帽子屋の顔をじ〜っと見つめ出したので、帽子屋は青くなってそわそわし始めました。
「証言をいたせ。それにびくびくするでない。さもなくばこの場で死刑に処するぞ」と王様は言いました。
これはまるで証人のはげましにはならなかったようです。帽子屋はしきりに足を踏み替え踏み替え、おどおどと女王様をうかがっていたかと思うと、うろたえのあまりにバタつきパンではなく、ティーカップをガブリと食いちぎってしまったんです。
ちょうどその時、アリスはとても奇妙な感じを覚え、すぐには何だか分からなくてずいぶんと戸惑ってしまいました。また大きくなり始めていたんです。ですからそうと分かるとはじめは席を立って法廷から出ていこうと思いました。でも、思い直して、いられるうちはそこにいることにしました。
「そんなにギュウギュウ押さないでくんないかな。ろくに息もできやしない」とヤマネが言いました。アリスの隣に座っていたんです。
「どうしようもないの。私、おっきくなってるの」アリスはとても小さくなって言いました。
「こんなとこでおっきくなる権利なんてないぞ!」
「バカ言わないで。ヤマネさんだっておっきくなってるでしょ」と今度はもっと大きな態度に出ました。
「ああ、だけど僕はまともな速さでだよ、そんなバカみたいななり方じゃなくてね」そう言ってヤマネは大むくれで席を立つと、法廷の反対側へと突っきっていってしまいました。
それまで女王様は帽子屋をじ〜っと見つめ続けていましたが、ちょうどヤマネが法廷を横切っていった時、廷吏の一人に言いました。「先の音楽会の歌い手の名簿を持ってまいれ!」これを聞いてあわれな帽子屋はふるえ上がってしまい、靴が両方とも脱げ落ちてしまいました。
 「証言をいたせ」王様は怒って繰り返しました。「さもなくば死刑に処するぞ、びくびくしていようがいまいがな」
「証言をいたせ」王様は怒って繰り返しました。「さもなくば死刑に処するぞ、びくびくしていようがいまいがな」
「あっしはしがない者にございます、陛下」帽子屋はふるえ声で証言を始めました。「ですんでお茶も始めてなかったんでございます――一週間かそこら以上も――それにバタつきパンはえらく薄切りになってまいりますやら――お茶のチラチラやらで――」
「何のチラチラじゃと?」
「その始まりがお茶と一緒だったんでございます」
「むろん、チラチラも茶も、チで始まるわ!」王様はビシッと言いました。「余を茶化しおる気か? 先を続けよ!」
「あっしはあわれな者にございます。それでそのあとはあれもこれもがチラチラいたしました――ただ、三月ウサギが申しまして――」
「申しません!」三月ウサギが大あわてでさえぎりました。
「言ったよ!」
「否認します!」
「あの者は否認しておる。そこのところは省け」と王様。
「ええ、とにかく、ヤマネが申しまして――」そう言って帽子屋はヤマネも否認するんじゃないかと不安げに振り返りました。でも、ヤマネは何も否認しませんでした。ぐっすりと眠りこんでいて。
「そのあと、バタつきパンをもう少しカットいたしました――」
「でも、ヤマネは何て言ったんですか?」陪審員の一匹がたずねました。
「それは思い出せません」
「思い出さねばならん。さもなくば死刑に処す」と王様。
あわれな帽子屋はティーカップもバタつきパンも落っことして、がっくりと片ひざをつきました。「あっしはつまらぬ者にございます、陛下」
「そちはつまってばかりおるではないか」
ここでモルモットの一匹が歓声を上げて、ただちに廷吏たちによって鎮静されました。(これは少しばかり難しい言葉なので、どんなふうにやったのか、ちょっと説明しましょう。廷吏たちは口のところがひもでくくれる大きなズックの袋を持っていました。その中にモルモットを頭からスルッと放りこんで、そのあと袋の上に鎮座したんです)
「良かった、今のが見られて。何度も新聞で読んだけど、裁判が終わった時、『拍手しようとする者があったが、ただちに廷吏によって鎮静された』っていうの。あれってどういうことか今までずっと分かんなかったし」とアリスは思いました。
「この件についてそれ以上何も知らんのであれば、下がって良い」と王様。
「これより下には下がれません。もう、すでに床の上におります」
「まさに下らん言い分じゃな」
ここでもう一匹のモルモットが歓声を上げ、鎮静されました。
「さあ、あれでモルモットはおしまいね! これでもっとスラスラ行くな」とアリスは思いました。
「お茶を済ませたいのですが」帽子屋は不安げに女王様をうかがいながら言いました。女王様は歌い手の名簿を見ています。
「行って良い」と王様。すると帽子屋は靴もほったらかしたまま、大急ぎで法廷から出て行きました。
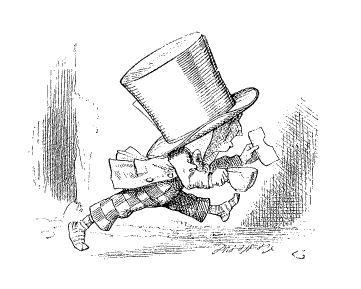
「――それと、ともかくおもてで首をはねておしまい」女王様が廷吏の一人に言い足しました。でも、廷吏が出入り口に達する間もなく、帽子屋は姿を消していました。
「次なる証人を召喚せよ!」と王様が言いました。
次なる証人は公爵夫人のコックでした。手にコショー入れを持っていたので、法廷に入ってくる前に、もうアリスには誰なのか見当がつきました。出入り口近くの者たちが、みんないっせいにくしゃみをし始めたんです。
「証言をいたせ」と王様。
「やだね」とコック。
王様がすがるような目を向けてきたので、白ウサギは声を低くして言いました。「この証人は陛下がお取り調べをせねばなりません」
「ふ〜む、せねばならんとあれば、せねばならん」王様は浮かない顔で言いました。そして腕組みをして、両目も埋もれんばかりにぐ〜っと顔をしかめてコックをにらみつけてから、重々しい声で言いました。「パイは何でできておる?」
「コショーさ、だいたい」とコック。
「トリ〜クル」と寝ぼけ声がその後ろで言いました。
「あのヤマネをひっとらえよ!」女王様が金切り声を上げました。「あのヤマネの首をはねよ! あのヤマネを法廷から叩き出せ! 鎮静せよ! つねり上げよ! ひげをむしってしまえ!」
しばらくはヤマネを追い出しにかかって、法廷中がごった返していました。そしてみんなが元通り落ちついた時には、もうコックは姿を消していました。
「気にせんで良い!」王様はいかにもホッとしたように言いました。「次なる証人を召喚せよ」そう命じると小声で女王様に言いそえます。「実はのう、お前や。次の証人の怒り調べは、ぜひともそなたがやっておくれや。余は怒り調べをすると、おでこが
アリスは白ウサギが名簿をごそごそ調べるのを見守りながら、次はどんな証人かな、とうずうずしていました。「――まだ、たいした証言は出てきてないもの」と心の中でつぶやきます。さあ、考えてみてください、どんなにアリスが驚いたことか。白ウサギがその細くて甲高い声をめいっぱいに張り上げて、読み上げた名前は、「アリス!」