その12
アリスの証言
「はい!」アリスは大声を上げ、ドッキリしたせいでここ数分でどれだけ自分が大きくなったのか、コロッと忘れてしまいました。そして大あわてでパッと立ち上がったので、スカートのすそで陪審員席をひっくり返し、陪審員を全員、下にいる大勢の頭の上にぶちまけてしまいました。そしてその場にみんな大の字になって伸びてしまい、アリスは前の週にうっかりひっくり返してしまった金魚鉢を、ありありと思い出しました。
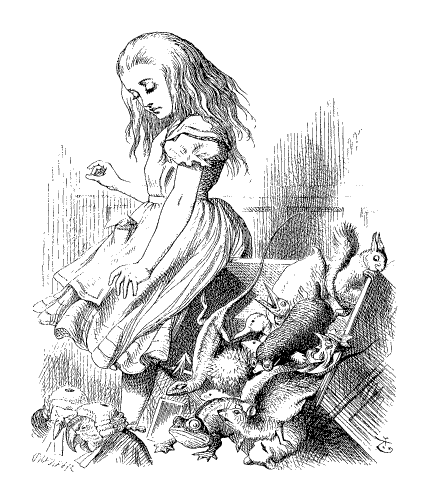
「あっ、ごめんなさいっ!」アリスはうろたえまくった声を上げ、できるだけ素早く元のところに陪審員たちを拾い集めにかかりました。金魚のことが頭から離れなかったので、すぐ集めて陪審員席に戻さなくちゃ、でないと死んじゃう、とそんな気がしてしまったんです。
「審理を続行することはできぬ、陪審員全員が所定の位置に戻るまではな」王様がえらくまじめな声で言いました。「――全員がじゃ」とことさらのように繰り返し、きびしい目でアリスを見据えます。
陪審員席を見ると、あわてたせいでトカゲをさかさまに突っこんでしまっていました。しかもかわいそうに、おチビちゃんはしっぽをぷらんぷらんと力なく振るばかりで、まるで身動きも取れずにいます。アリスはすぐにまた抜き出して、ちゃんと入れ直してあげました。「あんまり意味ないけど。どっちが上でも裁判にはおんなじぐらいしか役に立たないだろうし」と心の中では思いました。
ひっくり返されたショックからいくらか立ち直り、それぞれの石板と石筆も見つかって返してもらったとたん、陪審団はせっせせっせとこの事故の記録に取りかかりました。ただ、トカゲだけは別で、どうやらショックのあまり茫然自失の体で、口をぽかんと開けたまま、法廷の天井をじっと見上げているばかりでした。
「本件に関してそちは何を知っておる?」王様がアリスに言いました。
「なんにも」とアリス。
「まったく何もか?」となおも王様。
「まったくなんにも」とアリス。
「これはきわめて重要じゃな」王様は陪審団の方を向いて言いました。陪審団がそれを石板に書きとめにかかったちょうどその時、白ウサギが口をはさみました。「重要じゃない、とおっしゃっておられるのですね、もちろん」白ウサギはとてもうやうやしげに言いましたが、言いながらまゆをひそめて渋い顔をしていました。
「重要じゃない、むろん、そう言ったのじゃ」王様はあわてて言いました。でも、なおもぼそぼそとつぶやきました。「重要じゃな――重要じゃない――重要じゃない――重要じゃな――」とまるでどっちの言葉が響きがいいか、ためしているみたいでした。
陪審団の中には「重要じゃな」と書きとめる者もいれば「重要じゃない」と書きとめる者もいました。アリスは石板を見渡せるぐらい近くにいたので、これも見えましたが、「でも、どっちでもいいな」とこっそり思いました。
その時、しばらくせっせと何やら手帳に書きこんでいた王様が「静粛に!」と呼ばわると、その手帳を読み上げました。「規則第四十二条。身ノ丈一キロメートルヲ超エタル者ハ全テ法廷ヨリ退出スベシ」
全員がアリスに注目しました。
「私、1キロメートルもありません」
「あるとも」と王様。
「2キロメートル近くな」と女王様。
「いいわ、とにかく私は出ていかないです。だいたいそんなのちゃんとした規則じゃないもの。たった今王様がこしらえたんだから」
「これは記載されておるもっとも古い規則じゃ」と王様。
「だったら第一条のはずです」
王様は青くなり、あわてて手帳を閉じました。「評決を取りまとめよ」と小さなふるえ声で陪審団に命じます。
「まだ提出すべき証拠がございますので、陛下」白ウサギが大あわてでピョンッ、と飛び跳ねて言いました。「この文書が今しがた見つかりましてございます」
「何が書かれておるのじゃ?」と女王様。
「まだ開いてはおりません。ですが手紙だと思われます。被告人によって、その――誰かあてに書かれた」
「そうであったに相違あるまい」と王様。「誰でもない者あてに書かれたのでなければじゃが、そのようなことは普通ではないからのう」
「誰あてなんですか?」と陪審員の一匹が言いました。
「まったく誰あてにもなってはおりません。つまり、表書きは何もありません」白ウサギはそう言って文書を広げました。「結局、手紙ではありません。一編の詩であります」
「被告人の筆跡ですか?」と別の陪審員がたずねました。
「いえ、違います。で、それがこの証拠のもっとも奇妙な点であります」(陪審団はみんなわけが分からないといった様子です)
「被告人が誰かほかの者の筆跡をまねたに相違あるまい」と王様。(陪審団はみんなまたパッと明るい顔になりました)
「おそれながら陛下」とジャックが言います。「わたくしはそのようなものを書いてはおりませんし、わたくしが書いたとは証明できません。終わりに署名が何もないのですから」
「もしもそちが署名をしなかったのであれば、ことはいっそう悪くなるだけじゃ。そちは何か良からぬことをたくらんでおったに相違ない。さもなくば正直な者らしく、おのれの名をしるしたはずじゃ」
これには法廷中から拍手が起こりました。その日はじめて王様が述べた、真に冴えある意見だったんです。
「これにて被告人の有罪は、むろんのこと、明らかじゃ」と女王様。「では、この男の――」
「そんなこと何も明らかじゃないです! だって、その詩がどんなものかも分かってないもの!」とアリスは言いました。
「詩を読み上げよ」と王様。
白ウサギはめがねをかけました。「どこから始めましょうか、陛下?」
「はじめから始めよ」王様はまじめくさって言いました。「そして終わりが来るまで続けよ。来たらやめよ」
法廷がしーんと静まり返る中、白ウサギはこんな詩を読み上げました――
|
「そのものらわれにつたえり そなたかの かのものにむかいわがこといいおよびしと かのひとわれおせども われおよぐあたわずともいいしなりと
かのものそのものらにおくれり われゆきしことなかりきとのことばを (われらそれまこととしれり) かのひとことおしすすむるとあらば そなたいかなるさまにならんや
われかのひとに一あたえ そのものらかのものに二あたえ そなたわれらに三もしくはさらにあたえり そのものらみなかのものよりそなたへもどれり かつてわがものなりしかども
われもしくはかのひとたまさか このことまきこまるるとあらば まさしくわれらがありしさまさながら そのものらときはなつがため かのものそなたをたよるなり
われおもいたり そなたかつてかくありしなりと (かのひとかくいかりくるいしまえ) かのものとわれらみずからとそのもの そのうちさまたぐるものなりしと
かのものにしらるるなかれ かのひとそのものらもっともこのみしと これそなたみずからとわれのうちなる ほかなるいずれもよりまもらるる とわなるひめごとたるべきゆえ」 |
「これは我らがこれまでに得た、もっとも重要なる証拠じゃ」王様は嬉しそうに両手をこすり合わせて言いました。「それでは陪審団は――」
「もし陪審員の誰でも今の詩を説明できるんなら、そのヒトに500円あげるわ。(アリスはここ数分でとっても大きくなっていたので、王様の言葉をさえぎるのなんかちっとも怖くなかったんです)私は今の詩に意味なんかこれっぽっちもないと思うけど」
陪審団はみんな石板に書きとめました。「かのひといまのしにいみなんかこれっぽっちもないとおもう」でも、誰も詩の説明をしようとはしませんでした。
「もしもこの詩に何も意味がないのであれば、大いに手間がはぶけるじゃろうが、何も見出そうとせんで良いのじゃから。しかし、どうかのう」王様はひざの上に詩を広げ、片目で見つめました。「やはり、多少は意味があるように思えるのう。『――われおよぐあたわずともいいしなりと――』そちは泳げんのじゃろう?」とジャックに向かって言います。
ジャックは悲しげに首を振りました。「泳げるようにお見えですか?」(そうは確かに見えません。全身これ、紙なんです)
「ここまでは良し、と」そう言うと王様はその詩についてさらにぶつぶつとつぶやきました。「『われらそれまこととしれり』――これはむろん、陪審団じゃ――『かのひとことおしすすむるとあらば』――これは女王に相違あるまい――『そなたいかなるさまにならんや』――まったくじゃ!――『われかのひとに一あたえ、そのものらかのものに二あたえ』――なんと、これは被告人がパイをどうしたかということに相違あるまいが――」
「でも、『そのものらみなかのものよりそなたへもどれり』って続いてます」とアリス。

「そうとも、そら、パイはあるじゃろうが?」王様は得意満面で言い、テーブルの上のパイを指さしました。「これほど明白なことはない。しかし――『かのひとかくいかりくるいしまえ』――そなたは怒り狂ったことなどないと思うがのう?」と女王様にたずねます。
「あるものですか!」女王様はものすごい剣幕で言い、インクつぼをトカゲに投げつけました。(運の悪い小さなビルは石板に指で書くのはもうやめていました。跡がなんにも付かないのに気がついたんです。でも、今やあわててまた書き始めました、顔をしたたるインクを使って、インクの続く限り)
「するとここはいくらか狂いが生じておるわけじゃな」そう言って王様は笑みを浮かべて法廷を見回しました。しーんと静まり返っています。
「今のはしゃれじゃ!」王様は腹立たしげに付け加え、みんなは笑いました。「陪審団は評決を取りまとめるが良い」王様はその日二十回目ぐらいのセリフを言いました。
「駄目じゃ駄目じゃ! 刑の宣告が先じゃ――評決はあとじゃ」と女王様。
「バカげてるったらないわ! 刑の宣告が先だなんて!」アリスは大声で言いました。
「黙りおれ!」女王様は怒りで真っ赤になって言いました。
「黙んないわ!」
「この娘の首をはねよ!」女王様はあらん限りの声を張り上げました。誰も動きません。
「あなたなんか誰が気にするもんですか!(この時にはもう本来の大きさに戻っていました)あなたたちなんてただのトランプ一組じゃない!」
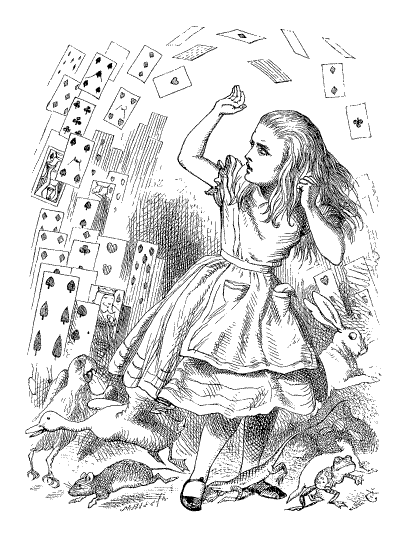
これを聞くとトランプ一組すべてが宙に舞い上がり、アリスに降りかかってきました。
アリスはギョッとして、カッともなって小さな叫び声を上げ、トランプを払いのけようとして――気がつくと、お姉さんのひざを枕に川辺に横たわっていました。お姉さんは木々の枝から顔に舞い降りた枯れ葉たちをやさしく払いのけてくれています。
「ほら、起きて、アリス!」お姉さんが言いました。「ほんとに、ずいぶん長いこと寝てたわねぇ!」
「わぁ、私、すごくおかしな夢を見ちゃった!」そう言うとアリスは思い出せる限りをお姉さんに話しました。たった今あなたが読んでいた、この奇妙なお話をです。そしてアリスが話し終えると、お姉さんはアリスにキスをして言いました。「本当におかしな夢ね。でも、もう急いでお茶に行きなさい。遅くなってるわ」そう言われてアリスは立ち上がると走り去っていきました。でも、走りながらもやっぱりまだ思っていました。なんてフシギな夢だったんだろう、ってね。
=========================
でも、お姉さんはアリスが行ってしまっても、そのままじっと座っていました。ほおづえをついて、夕日をながめながら、小さなアリスのことや、そのフシギな夢の話のあれこれを思い浮かべていたんです。するとそのうちにお姉さんもうつらうつらと夢を見始めました。そしてこれがお姉さんの見た夢です――
まず夢に現れたのは、ほかでもない、小さなアリスでした。再び小さな両手がこちらのひざの上で握り合わされて、キラキラした目がまっすぐにこちらの目を見上げています――その声も実に生き生きと聞こえましたし、しょっちゅう目に入ろうとするほつれ毛を、頭をクンと振ってはねのけるのも見えました――そしてなおも聞いたところでは、と言うか聞いたらしいところでは、まわり中が妹の夢に現れたおかしな人や動物たちでいっぱいになったんです。
丈の高い草が足元でカサカサと音を立て、白ウサギが走り過ぎていきました――おびえたネズミがパチャパチャとしぶきを上げて、近くの淵を泳いでいきました――ティーカップのカチャカチャという音が、三月ウサギと仲間たちが終わりのないお茶会を開いている音が聞こえますし、女王様の甲高い声も、不運なお客たちに死刑を言い渡している声も聞こえます――再びブタ赤ちゃんが公爵夫人のひざに抱かれてくしゃみをしていますし、そのまわりでは大皿小皿が砕け散っています――再びグリフォンの金切り声が、トカゲの石筆のキーキーきしる音が、そして鎮静されたモルモットたちの苦しげなうめき声が、と、それらがあたりを満たして、遠くから聞こえてくる、あわれなウミガメフーのすすり泣く声と混じり合いました。
そんなふうにお姉さんは目を閉じたままずっと座っていて、自分がフシギの国にいることをなかば信じたんです。もっとも目を開けてしまったら、それだけで何もかもがありふれたつまらないものに変わってしまうだろうと分かってもいましたが――草は風に吹かれてカサカサと鳴っているだけ、そして淵は葦のそよぎにさざ波を立てているだけでしょう――ティーカップのカチャカチャという音は羊たちのベルが鳴るカランカランという音に、そして女王様の甲高い叫び声は羊飼いの男の子の声に変わるでしょう――それに赤ちゃんのくしゃみや、グリフォンの金切り声や、そのほかの奇妙な音は(お姉さんには分かっていました)、どれもこれも忙しい農家のごちゃ混ぜの喧騒に変わってしまうでしょう――そして遠くで鳴いてる牛たちの声が、ウミガメフーの重っ苦しいすすり泣きに取って代わるでしょう。
最後にお姉さんは、ほかでもない、この小さな妹が、将来どんな大人になるのか思い描いてみました。きっと大人になってからも、ずっと子供の頃のすなおでやさしい心をなくさないでいてくれるだろう。そして小さな子供たちをまわりに集めては、おかしなお話をいくつもしてあげて、その子たちの目をキラキラと輝かせて夢中にさせるだろう。もしかしたら、昔見たフシギの国の夢のことまで話してあげて。そして子供たちが悲しむと自分も悲しくなって、子供たちが喜んでくれると自分も嬉しくなって、そんな時には思い出しているだろう。自分自身の子供の頃を、そして幸せな夏の日々のことを。
おわり