ウサギが小さなビルをおったてる
あの白ウサギです。ちょこちょこと少しずつこちらに戻ってきます。でも、きょろきょろとあたりを見回していて、何か落とし物でもしたみたいです。それにぶつぶつとつぶやいているのも聞こえました。「公爵夫人! 公爵夫人! あ〜なんてこった! あ〜まいったなほんとにもう! あの方に死刑にされちまうよ、イタチを見るより明らかだ! いったいどこに落としちまったんだろう?」せんすと手袋を捜してるんだとすぐに察しがついたので、実に親切にアリスもあたりを捜してみましたが、どちらもどこにも見あたりません――涙の海で泳ぐ前とは何もかもが変わってしまったらしく、大きなホールはガラスのテーブルや小さな扉ともども、あとかたもなく消え失せてしまっていたんです。
あたりを捜しているとすぐにウサギが気がついて、怒ったような声で呼びかけてきました。「なんだメアリ・アン、こんなとこで何をやっとるんだ? 今すぐ家まで飛んでって、手袋とせんすを取ってきてくれ! そら、早く!」するとあんまりびっくりしたものですから、アリスはウサギの勘違いを正そうともせず、すぐにウサギの指さした方に走っていきました。
「お手伝いさんと間違えたんだ」アリスは走りながら思いました。「私が誰だか分かったらどんなに驚くかな! でも、せんすと手袋は持ってってあげなくちゃ――と言っても見つけられたらだけど」そう言った時、ぱったりと一軒の小ぎれいな家の前に出ました。扉にはピカピカのしんちゅう製のプレートが付いていて、「白 兎」と名前が彫ってあります。アリスはノックせずに中に入ると二階へと急ぎました。本物のメアリ・アンにばったり会って、せんすと手袋を見つける前に家から追い出されちゃうんじゃないかな、とびくびくしていました。
「すごく変な感じ、ウサギのお使いをしてるなんて! この次なんてダイナにお使いさせられてるんじゃないかな!」そう思ってアリスは起こりそうなことを想像してみました。「『アリスお嬢様! すぐにこちらにいらして散歩の支度をなさってください!』『すぐ行くわばあや! でも、ダイナが戻ってくるまでこのネズミの穴を見張って、ネズミが逃げ出さないようにしなくちゃいけないの』――ただ、そんなふうに人にあれこれ言いつけ出したら、みんなダイナをおうちに置いといてくれないだろうな!」
この時にはもう、きれいに片付いた小さな部屋の中に入っていました。窓際にテーブルがあって、その上に(期待した通り)せんすが一本と、小さな白い手袋が二、三足載っています。そのせんすと手袋一足を取り上げて部屋から出ようとしたちょうどその時、鏡のそばに置かれた小さなびんに目がとまりました。今度は「飲んで」と書かれたラベルはありませんでしたが、それでもアリスは栓を抜いてびんに口をつけました。「何かおもしろいことが起こるはずだもの、何かを食べたり飲んだりすれば」とアリスは思いました。「だからこのびんもどうなるかちょっと見てみよう。ぜひまたおっきくしてほしいな。ほんとにこんなにちっぽけなままなのはいいかげんうんざりだもの!」
本当にそうなりました。しかも思ったよりもずっと早くです。びんの半分も飲まないうちに頭が天井にぎゅうぎゅうと押しつけられ、首の骨が折れないようにかがまなければならなかったんです。アリスはあわててびんを置き、こう思いました。「もういいよ――これ以上おっきくなんないでほしいな――今だってもうドアから出られないし――ほんとにこんなにたくさん飲まなきゃ良かった!」
残念! そう思っても、もう手遅れです! アリスはどんどん大きく、大きくなって、たちまち床にひざをつかなければならなくなりました。少しするとそれでもきつくなったので、片ひじをドアに押し当て、もう片方の腕を頭に巻いて横になってみました。それでもまだ大きくなっていくので、これが最後の手、と片手を窓の外に出し、片足を暖炉の煙突に突っこんで、こう思いました。「もう何が起きてもこれ以上どうしようもないよ。私、どうなっちゃうの?」

幸いにも、小さな魔法のびんのききめはもうめいっぱいで、それ以上大きくはなりませんでした。それでもきゅうくつでしょうがないし、どう見ても、もう部屋から出られそうになかったので、暗い気持ちになったのも無理はありません。
「おうちの方がずっと良かった」とかわいそうに、アリスは思いました。「しょっちゅうおっきくなったりちっちゃくなったりしてなかったし、ネズミやウサギにあれこれ言いつけられてもいなかったし。あのウサギ穴なんかにもぐりこまなきゃ良かった――でも――でも――ちょっとおもしろいよね、こんなのも! ほんとに私、どうしちゃったんだろ! おとぎ話を読んでた頃は、そんなこと起きっこないように思ってたのに、今ここじゃそのまっただなかにいる! 私のことを書いた本があるべきよ、当然そうよ! じゃあおっきくなったら自分で書こう――でも、もうおっきくなっちゃってる」アリスは悲しそうに言いました。「少なくとも、ここじゃもうこれ以上おっきくなんてなりようがないよ」
「でも、だったら私、今よりも絶対に歳を取らないの?」とアリスは思いました。「それならホッとするとこもあるな――絶対におばあさんにならない――でも――そしたらずうっとお勉強がある! わぁ、そんなのはやだなぁ!」
「もぅ、馬鹿ねアリス!」アリスは自分に答えました。「どうやってここでお勉強するの? だってあなたでほとんどいっぱいで、教科書を広げる場所なんてどこにもないじゃない!」
そしてそんなふうにまず一方、次にもう一方と、まったくみごとなやりとりをしながらおしゃべりを続けました。でも、しばらくするとおもてから声が聞こえてきたので、おしゃべりをやめて耳をそばだてました。
「メアリ・アン! メアリ・アン! 今すぐ手袋を持ってこい!」とその声は言いました。それからパタパタという小さな足音が階段を上ってきました。ウサギが自分を捜しに来たんだと分かったので、アリスはブルブルふるえて家までガタガタ揺らしました。今ではウサギの千倍ぐらい大きいのだし、怖がる理由なんか何もないのをコロッと忘れていたんです。
間もなくウサギはドアまでやってきて開けようとしました。でも、ドアは内開きで、アリスのひじがギュッと押しつけられていたので、いくらやっても駄目でした。ウサギがつぶやくのが聞こえます。「じゃあ、おもてに回って窓から入ろう」
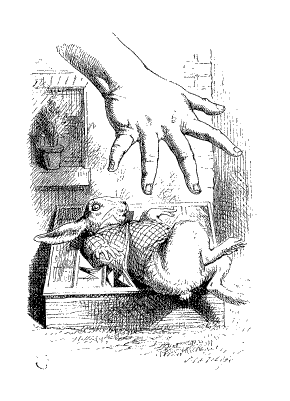 「そんなことさせない!」そう思ってアリスはウサギが窓の真下に来るのを音を聞いて待ち、来た、と思うとパッと手を広げてつかみかかりました。何もつかめませんでしたが、小さな悲鳴とドシン、ガチャンという音が聞こえたので、ウサギさんがキュウリの温床か何かにころげこんだんじゃないかな、と思いました。
「そんなことさせない!」そう思ってアリスはウサギが窓の真下に来るのを音を聞いて待ち、来た、と思うとパッと手を広げてつかみかかりました。何もつかめませんでしたが、小さな悲鳴とドシン、ガチャンという音が聞こえたので、ウサギさんがキュウリの温床か何かにころげこんだんじゃないかな、と思いました。
次に聞こえてきたのは怒った声でした――ウサギのです――「パット! パット! どこにおる?」それからこれまでに聞いたことのない声が、「へーい、ここにおりやす! リンゴを掘っとりやすで、だんな様!」
「リンゴを掘っとるだと、まったく!」ウサギは怒って言いました。「こっちだ! こっちに来てこいつから私を出してくれ!」(さらにガラスの割れる音)
「ところで聞くがパット、窓の中のありゃ何だ?」
「へぇ、ありゃ腕ですな、だんな様!」(「んで」というふうに言いました)
「腕だと、このトンマ! あんなデカさのがあるもんか。そら、窓をまるまるふさいじまっとるぞ!」
「へぇ、ふさいどりやすな、だんな様。そんでもやっぱありゃ腕ですな」
「まあいい、とにかくありゃ無用のデカブツだ。行って取っ払ってくれ!」
そのあとは長いことずっと静かで、時々ひそひそ声が、たとえば「へぇ、あの手は苦手でさ、だんな様、どうにもこうにも!」「言う通りにしろ、この臆病者が!」といったものが聞こえてくるだけだったので、とうとうアリスはまた手を広げてもう一度つかみかかりました。今度は小さな悲鳴が二っつと、さらにガラスの割れる音が聞こえました。「ずいぶんたくさんキュウリの温床があるんだな!」とアリスは思いました。「次はどうするのかな! 窓から引っぱり出すっていうのが、ウサギさんたちにできればいいのに! ほんとに私だってこれ以上こんな中にいたくないもの!」
それっきり何も聞こえないまましばらく待ちました。ようやく聞こえてきたのはゴロゴロという小さな車輪の音と、わいわいがやがやしゃべっている、かなり大勢の声でした。こんな言葉が聞き取れました。「もう一個のはしごはどうした?――いや、おら一個しか持ってこねえで良かったんだ。もう一個はビルだ――ビル! そいつをこっちに持ってこいや!――ほら、そいつらをこの角に立てろ――そうじゃねえ、まずそいつらをつないで縛れ――まだ半分の高さにも届かねえぞ――ったく、充分用は足りるって。細けえこと言うんじゃねえよ――ほら、ビル! このロープをつかめ――屋根はでえじょぶか?――あのかわらゆるんでんぞ、気ィつけろ――うわ、落っこってきた! 頭ァ引っこめろ!」(ガッシャン!)――「おい、誰がやったんだ?――ビルだな、たぶん――誰が煙突をおりてくんだ?――やだよ、おらやんねえ! おめえがやんな!――そんなのおらもごめんだ!――ビルがおりてくしかねえよ――おい、ビル! ご主人様がおめえに煙突をおりてってくれとよ!」
「あれ! じゃあビルが煙突をおりてこなくちゃなんないのね?」とアリスは思いました。「でも、みんななんでもかんでもビルに押しつけてるみたい! ビルの代わりには絶対になりたくないな。この暖炉って確かにせまいけど、でも、ちょっと蹴るぐらいはできそう!」
アリスは煙突に突っこんだ足をできるだけ引き下げて、小さな動物(どんな動物かは見当がつきませんでした)が煙突の中でカリカリもぞもぞやっているのが、すぐ上に聞こえてくるまで待ちました。それから心の中で「これが」とつぶやくと、「ビル」でキョーレツな一蹴りをおみまいして、次はどうなるかと様子をうかがいました。
 まず聞こえたのはみんながいっせいに上げた声で、「ビルが飛んだぁ!」次にウサギだけの声――「受けとめろ、おまえら、垣根のとこの!」そして静寂、それからまたてんでの声――「頭を支えてやれ――ほら、ブランデーだ――むせさすな――なあ、どんなだった? 何があったんだ? みんな話してくれや!」
まず聞こえたのはみんながいっせいに上げた声で、「ビルが飛んだぁ!」次にウサギだけの声――「受けとめろ、おまえら、垣根のとこの!」そして静寂、それからまたてんでの声――「頭を支えてやれ――ほら、ブランデーだ――むせさすな――なあ、どんなだった? 何があったんだ? みんな話してくれや!」
最後に聞こえてきたのは小さくて弱々しい、キーキーした声で(「あれがビルね」とアリスは思いました)、「あぁ、おいらにもよく分かんねえ――もういいよ、あんがと。だいぶ良くなった――でも、頭ん中ぐちゃぐちゃで何つったらいいんだか――覚えてんのったら、なんかがびっくり箱みてえに飛び出てくんのと、おいらがすっとんでくのだけなんだ。まるでロケット花火みてえに!」
「そんなだったよ、ほんとに!」とほかのみんなが言いました。
「家を焼いちまうしかない!」とウサギの声が言いました。アリスは思いっきり大声で叫びました。「そんなことしたら、ダイナをけしかけるからね!」
たちまちし〜んと静まり返ったので、アリスは一人考えました。「次はどうする気かな! ちょっとでも頭があれば、屋根をはがすんだろうけど」少しするとまた何やらわさわさし始めて、ウサギがこう言うのが聞こえました。「手押し車一杯でいいだろう、とりあえず」
「手押し車一杯の、何?」とアリスは思いました。でも、あれこれ考えているひまはありませんでした。次の瞬間、窓から小石が雨あられとバラバラ降りそそいできて、いくつか顔にも当たったんです。「こんなのやめさせよう」そう思ってアリスは大声で叫びました。「もう一度やったら承知しないから!」と、これでまたし〜んと静まり返りました。
アリスはあれっ、と思いました。見ると床にころがった小石がみんな小さなケーキ菓子に変わっていくんです。そこでひらめきました。「このお菓子を食べれば、きっと体の大きさがどうにか変わるわ。で、これ以上おっきくはとてもなれないから、きっとちっちゃくなるはずよ」
そこでお菓子を一つパクッと食べてみると、たちまち体が縮み出したのでアリスは大喜びです。ドアを通り抜けられるぐらいに小さくなると、すぐに家から飛び出しました。ところがおもてに出てみると、そこには小さな動物や鳥たちがかなり大勢待ちかまえていました。かわいそうな小さなトカゲ、ビルがそのまんなかにいて、二匹のモルモットに支えられ、びんから何かを飲ませてもらっています。みんなはアリスが姿を見せたとたん、ドッと押し寄せてきました。でも、アリスは必死に走って逃げたので、ほどなくして気がつくと、うっそうとした森の中に無事に逃げおおせていました。
アリスは森の中をさまよいながら思いました。「一番にしなくちゃなんないのは、もう一度ちゃんとした大きさになること。で、二番目があの素敵なお庭への道を見つけること。これが一番いい計画だろうな」
確かに素晴らしい計画に思えますし、とてもすっきりと分かりやすくまとめられています。たった一つの問題は、どうやってその計画に取りかかるのか、これっぱかりの考えも浮かばないことでした。そこで何か見つからないかと木々の間で目をこらしてあたりを見回していたところ、小さくワンッと吠える声が頭の真上で聞こえたので、アリスは大あわてで上を見ました。
巨大な子犬が大きなまんまるい目で見おろしていて、そろそろと前足を伸ばしてきて、こちらにさわろうとしています。「いい子ね、よしよし!」アリスはあやすように言って、いっしょうけんめい口笛を吹いてやろうとしました。でも、そうしながらも、おなかをすかしてるのかも、と思うと怖くてしかたがありませんでした。もしそうだったら、どんなにあやしたところで、きっとパクッと食べられてしまうでしょう。
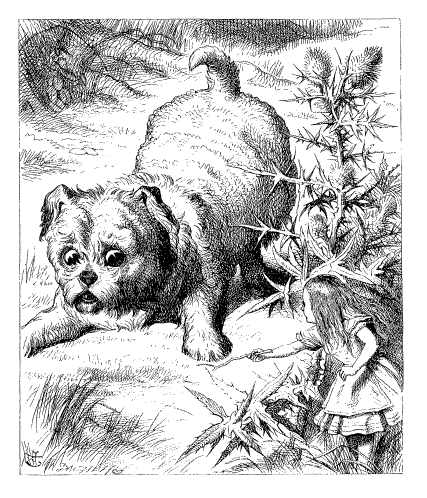
ほとんど無意識に、アリスは小枝の切れ端を拾い上げると子犬に向かって差し出しました。するとたちまち子犬は大喜びでキャンッと吠えてピョンッと跳ね、小枝に飛びかかってきてじゃれつきました。そこでアリスは踏みつぶされないように大きなアザミの後ろにさっと身をかわしました。と、反対側から出たとたん、子犬はまたもや小枝に飛びかかってきましたが、あわてて飛びついたせいで頭っからごろんとひっくり返ってしまいました。そこでまるで荷馬車のお馬と遊んでるみたい、と思いながら、そして今にも踏みつぶされるんじゃないかとヒヤヒヤしながら、またアザミをぐるっと回って逃げました。すると子犬は小枝めがけて短い突撃を繰り返し始め、ダダッと小さく駆け寄ってはそのたびにうんと大きく駆け戻り、その間ずっとしゃがれっ声でワンワン吠えていましたが、ついにはかなり離れたところに座りこんでしまい、舌をたらしてヘッヘッとあえぎながら、大きな両目もなかば閉じてしまいました。
逃げるなら今だ、とアリスは思いました。そこですぐに駆け出し、へとへとになって息が切れてしまうまで走って、ようやく子犬の吠える声は遠くでほんのかすかに聞こえるだけになりました。
「だけどすごくかわいいワンちゃんだったなぁ!」アリスはキンポウゲにもたれて休みながら、その葉の一枚で自分をあおいで言いました。「ほんとに芸を教えてあげたかったけど、もし――もし私さえちゃんとした大きさだったら! あ、いっけない! もうちょっとで忘れるとこだった。もう一度おっきくなんなくちゃ! えっとぉ――どうすればそうなれるのかな? きっと何かを食べたり飲んだりするはずよ。でも、一番の問題は、『何を?』」
一番の問題は確かに「何を?」でした。まわりの花や草の葉をぐるりと見回しましたが、こういう場合に食べたり飲んだりするのにふさわしそうなものは何も見あたりません。近くに大きなキノコが一本生えていましたが、自分と同じぐらいの背たけがあります。そこでその裏側を見て、両脇を見て、後ろも見たところで、てっぺんにも何があるか見てみた方がいいな、と思いつきました。
爪先立って背のびをして、キノコのへりからのぞいてみると、いきなり目と目が合いました。大きな青いイモムシです。イモムシはキノコのてっぺんに座っていて、腕組みをして、長い水ギセルで静かにタバコをくゆらせていて、アリスもほかの何もかも、まるでムシしていました。