その1
鏡のおうち
一つだけは確かです。白の子猫はそのことには何の関わりもなかったっていうこと――それはまるっきり黒の子猫のせいだったんです。白の方はこの10何分というもの、ずっとお母さん猫にお顔を洗われていたんですから(それにおおむねのところ、とってもよく我慢していました)。ですからね、その子がいたずらに何か手を貸したりしたはずがないんです。
ダイナが子猫の顔を洗うやり方っていうのはこうです。まず、かたっぽの前足でおチビちゃんの耳のあたりをギュッと押さえつけ、それからもうかたっぽの足で、鼻から始めて顔中くまなく、毛を逆撫でするようにこするんです。そしてちょうど今は、さっきも言ったように、白の子猫にせっせと取りかかっていて、子猫はじっとうずくまったまま、のどをゴロゴロ鳴らそうとしています――きっとこれはみんな自分のためなんだと思っているんでしょう。
でも、黒の方は午後のもっと早い時間に済ませてもらっていたので、アリスが大きな肘掛け椅子のすみっこに丸くなって、ひとりごとをつぶやきながらうとうとしている間、巻き終えかけていた毛糸玉をかっこうのおもちゃにして、あっちにコロコロ、こっちにコロコロと、毛糸がすっかりほどけてしまうまで跳ね回って遊んでいたんです。で、この通り。毛糸は暖炉の前の敷物一面に広がって、どこもかしこも絡まり合ってこんがらがり、そのまんなかで子猫が自分のしっぽを追いかけ回しているんです。
「ああ、もう、ほんっとに悪い子なんだから!」アリスは声を上げて子猫をパッとつかまえると、困った子だと思われていることを分からせるために、軽くキスしてやりました。「ほんとに、ダイナがもっとちゃんとしたお行儀をあなたに教えるべきだったのよ! そうよダイナ、そうだったんだからね!」アリスはとがめるようにお母さん猫を見て、せいいっぱい不機嫌な声で言い――それから子猫と毛糸を抱えて肘掛け椅子によいしょとのぼると、もう一度毛糸玉を巻き直しにかかりました。でも、あまり手早くはありません。子猫に話しかけたり、ひとりごとを言ったりと、ずっとおしゃべりをしていたからです。キティはアリスのひざの上にお澄ましして座っていて、毛糸の巻かれる進み具合を見守るふうを装いながら、時々前足を伸ばしては毛糸玉にそっと触れていました。まるでよろしければ喜んでお手伝いしますよ、とでも言うように。
「明日は何の日か分かる、キティ? もしも私と一緒に窓のとこにいたら分かったでしょうね――ただ、ダイナにおめかししてもらってたから無理だったけど。かがり火のための薪を集めてる男の子たちを見てたの――かがり火にはたっくさん薪がいるのよ、キティ! ただ、すごく寒くなって、雪もうんと降ってきたから、途中でやめなくちゃなんなかったけど。心配しないで、キティ。明日はかがり火を見に行こうね」そう言うとアリスは子猫の首に毛糸を二、三回巻き付けました。似合うかな、と、ちょっとためしてみたんです。これで子猫は大あわて。おかげで毛糸玉は床にころがり落ちて、また長々とほどけてしまいました。
「分かってる? 私、すごく怒ってたのよ、キティ」アリスは毛糸玉と子猫とともに元のように椅子にくつろぐと、すぐにまたおしゃべりを始めました。「あなたのやってた悪さが全部分かった時、もうちょっとで窓を開けて、雪の中にあなたをほっぽり出すとこだったわ! でも、そうされても当然だったのよ、このいたずらっ子のおチビちゃん! 何か言いわけがある? さあ、最後まで聞いて!」アリスは指を一本立てて言いました。「あなたの悪さを全部言ってあげる。一つ目。今朝ダイナにお顔を洗ってもらってる時、二度も大きな声でわめいた。さあ、違うなんて言わせないわよ、キティ。私は聞いたんだから! え、何?」(子猫が話しかけてるっていうふりをしながら)「お母さんの手が目に入った? あぁ、それはあなたが悪いのよ、お目々を開けっぱなしにしてたんだから――もしもぎゅっとつむれば、そんなことにはならなかったわ。さあ、もうそれ以上言いわけはやめて、聞くの! 二つ目。スノードロップの前にミルクのお皿を置いたとたん、しっぽをひっぱってあの子を遠のけた! え、のどが渇いてたって? あの子だってのどが渇いてたかもしれないでしょ? さあ、三つ目よ。私が見てないうちに毛糸をすっかりほどいちゃった!
「これで悪さは三つよ、キティ。しかも、どの分の罰もまだ受けてないのよ。そう、罰は全部ためてあるの、来週の水曜日までね――私の罰も全部ためてあったらどうしよう?」子猫に話していると言うよりひとりごとになっています。「一年の終わりにどんなことされるんだろう? きっと牢屋に入れられるんだ、その日が来たら。でなかったら――えっとぉ――どの罰も夕ごはん抜きってことだったら? そのヒドイ日が来たら、一度に50回分も夕ごはんを抜かなくちゃなんない! いいわ、そんなのたいして気にしないもの! それだけ食べるよりは抜かれる方がずっとましよ!
「窓のガラスに雪の当たる音が聞こえる、キティ? とってもやさしい、やわらかな音ね! まるで誰かがお外で窓じゅうにキスしてるみたい。雪って木や野原がとっても好きなのかな? あんなにやさしくキスしてあげるなんて。それにすっぽりとおおってもあげるし、ほら、白いキルトでね。そしてこう言うのかも。『お眠りなさい、みんな、また夏が来るまでね』って。そして木や野原は夏に目を覚ますとね、キティ、みんな緑のお洋服を着て、あっちこっちでダンスをするの――風が吹くたびに――あぁ、とってもきれい!」アリスは思わず声を上げ、手を打ったはずみに毛糸玉を落としてしまいました。「でも、ほんとにそれがほんとならいいのに! 森って秋には眠そうに見えると思うの、葉っぱが茶色くなってきてるとね。
「キティ、チェスはできる? ほら、笑わないでよ、私はまじめに聞いてるの。だってついさっき私たちがやってた時、まるで分かってるような顔でじっと見てたじゃない。それに私が『チェック!』って言ったら、のどをゴロゴロ鳴らしたわ! そうね、あれはうまい詰めだったわ、キティ。それにほんとに私が勝てたかもしれなかったし、あの意地悪な
でも、これではアリスが子猫にしている話から離れていっちゃいます。「ごっこ遊びしよう、あなたは赤の
「さあ、もしもちゃんとお耳を傾けて、おしゃべりをひかえてさえいるならね、キティ、私が鏡のおうちについて知ってることを全部教えてあげる。まず、鏡越しに見えてるお部屋があるでしょ――あのお部屋はうちの居間とまるで一緒なんだけど、ただ、物が反対向きになってるの。椅子にのぼるとお部屋が全部見えるわ――暖炉の真後ろのとこ以外はね。あぁ!ほんとにそこのとこが見えたらいいのに! 冬には火を入れてるのかどうか、とても知りたいの。分かんないものよ、ほら、こっちの火が煙を出して、あっちのお部屋でも煙が上がんないと――でも、煙はただの見せかけで、火を入れてるみたいに見せてるだけかも。それと、ご本はこっちにあるご本とよく似てるけど、ただ、言葉が逆向きになってるの。それは分かってるわ。だってこっちのご本を一冊、鏡にかざしたことがあって、そしたら向こうのお部屋でもかざしてきたんだもの。
「鏡のおうちで暮らすのはどう、キティ? あっちでもミルクはもらえるのかな? もしかしたら鏡のミルクは飲めないのかも――でも、あっ、キティ! ほら、廊下に来たわ。鏡のおうちの廊下はちょっとだけのぞいてみることはできるのよ、うちの居間のドアを大きく開けとけばね。で、見えてる限りはうちの廊下にそっくりだけど、ただね、その向こうはまるで違ってるかもしれないの。あぁ、キティ、鏡のおうちに入ってけたら、もう、どんなにいいだろね! きっとおうちの中には、あぁ!とってもきれいな物があるわ! ごっこ遊びしよう、なんとか中に入ってく方法があるのよ、キティ。そう、鏡がみんなガーゼみたいに柔らかくなって、通り抜けられるの。あれっ、ほら、ほんとに霧みたいになってく! とても簡単に通り抜けられるようになるわ――」そう言っているうちにアリスは暖炉の飾り棚の上に乗っていました。でも、どうやってのぼったのかは自分でもよく分かりません。そして本当に鏡は、まるでキラキラと輝く銀色の霧のように溶けて消え始めていました。
次の瞬間にはアリスは鏡を通り抜けて、鏡のお部屋の中にぴょんと飛び降りていました。真っ先にしたのは暖炉に火があるかどうか見ることです。すると本物の火があったので、かなり満足でした。あとにしてきたお部屋の暖炉と同じぐらい明るく燃えさかっています。「じゃあ、こっちでも元のお部屋にいたのとおんなじぐらいあったかでいられるな」とアリスは思いました。「と言うか、もっとあったかだな。こっちには火に近づかないようにガミガミ言う人は誰もいないもの。うわぁ、とってもおもしろいだろな、鏡越しにこっちに私が見えて、でも、手は届かないなんて!」
それからアリスはお部屋を見回し始め、そして気がつきました。元のお部屋から見えたものはごく普通でおもしろみはないんですが、そのほかはみんなこれ以上ないぐらいに変わっているんです。たとえば暖炉わきの壁にかかっている絵はどれもみんな生きているみたいですし、暖炉の飾り棚の置き時計にさえ(ほら、鏡の中に見えるのは時計の後ろ側だけでしょう)小さなおじいさんの顔があって、アリスににっこりと笑いかけたんです。
「こっちのお部屋は向こうほどきちんとしてないな」とアリスは思いました。炉床の燃えがらの中にチェスの駒がいくつか落ちているのに気がついたんです。でも、次の瞬間、「えっ!」と小さな驚きの声を上げ、四つんばいになって駒たちをじっと見つめていました。チェスの駒が二つずつ組んで歩き回っています!
「ここに赤の
その時、後ろのテーブルの上で、何かが甲高い声で泣き出したので、振り向いてみたところ、ちょうど白の
「あの子の声だわ!」白のクイーンが大声を上げて猛然と走り出し、勢いあまって通り過ぎざまキングを燃えがらの中に引っくり返しました。「かわいいリリー! わたくしの王女ちゃん!」そう言って囲いの柵の側面をやみくもによじ登り始めます。
「王女ちゃん、ちゃんちゃらじゃ!」キングは鼻をさすりながら言いました。ころんだ拍子にぶつけたんです。少しはクイーンに腹を立てても無理のないことでした。なにしろ頭のてっぺんから爪先まで灰まみれになってしまったんです。
アリスはなんとか役に立ちたいと思っていました。そしてかわいそうに小さなリリーは今にもひきつけを起こしそうに泣き叫んでいたので、とにかく早くと、クイーンをつまみ上げてテーブルの上のやかましい小さな娘のそばに置いてあげました。
クイーンは息をのみ、座りこんでしまいました。空中をヒュッと飛んできたのですっかり肝をつぶしてしまったんです。そして1、2分はものも言わずに小さなリリーを抱きしめるばかりでした。少し息が落ち着くと、すぐにクイーンは白のキングに大声で呼びかけました。キングは灰の中にふくれっ面で座りこんでいます。「火山に気をつけて!」
「何、火山じゃと?」キングは顔を上げて不安げに暖炉の火を見ました。そこが一番ありそうな場所だと思ったみたいです。
「わたくしを――吹き上げ――ましたの」クイーンはあえぎながら言いました。まだちょっと息を切らしています。「よろしいこと、普通の方法で――登ってらっしゃるのよ――吹き上げられないで!」
アリスは白のキングがよっこらしょ、やっこらしょ、と柵の横棒を一段一段よじ登っていくのをしばらく見守っていましたが、ついにはこう言いました。「あのぉ、その調子だと、テーブルにたどり着くのに何時間もかかっちゃいますよ。私がお手伝いした方がずっといいんじゃないですか?」でも、そう聞いてもキングはまるで気づいてくれません。声も聞こえていなければ姿も見えていないのはもう明らかでした。
そこでアリスはキングをそぅっとつまみ上げると、キングが肝をつぶしてしまわないように、クイーンの時よりもゆっくりと運んであげました。でも、テーブルに置く前に、ちょっと灰を払ってあげた方が良さそうだと思いました。それぐらい灰まみれだったんです。
その時のキングのお顔ったら生まれてから一度も見たことないようなお顔だったわ、とアリスはあとで言いましたが、見えない手で空中に持ち上げられて灰を払われていると気がつくと、キングは驚きのあまりに叫ぶこともできなくて、目と口ばかりがどんどん大きく、どんどんまん丸になっていったので、とうとうアリスは笑ってしまって手がふるえ、もうちょっとでキングを床に落っことしてしまうところでした。
「ねえ、お願い、そんなお顔しないで!」アリスは思わず大声で言いました。キングには聞こえていないのをコロッと忘れています。「あなたが笑わせるからちゃんと持っててあげられないの! それにお口をそんなに大きく開けておかないで! 灰が全部入っちゃいます――さあ、これでまあ、きれいになったと思います!」アリスはそう言ってキングの髪をなでつけてあげて、テーブルの上のクイーンのそばに置いてあげました。
とたんにキングは後ろ向きにぱったりと倒れてしまい、そのままぴくりともしません。それを見てアリスは、大変なことしちゃったかも、と、ちょっと不安になって、キングにかけてあげるお水はないかと部屋をぐるっと回って探してみました。でも、インク瓶一つしか見つからなかったので、それを持って戻ってみると、キングはもう息を吹き返していて、おびえた小さな声でクイーンと話をしていました――あんまり小さな声なので、何を話しているのかアリスにはほとんど聞き取れません。
キングはこう言っていました。「本当じゃよ、お前。余はまさしく
これにクイーンが答えて、「あなたには
キングはさらに、「あの瞬間の恐ろしさは、余は絶対に、絶対に忘れんよ!」
するとクイーンは、「でも、忘れてしまいますわ、そのことを書き留めておきませんと」
アリスが興味深く見つめる中で、キングはポケットからとんでもなく大きな備忘録を取り出すと、それに書きこみ始めました。ふいにアリスは思いついて、キングの肩の上にかなり突き出ている鉛筆のはしをつかむと、キングの代わりに書きこみ始めました。
かわいそうに、キングは戸惑いと不安の色を浮かべて、しばらくの間、何も言わずに鉛筆と格闘していました。でも、アリスの方がずっと力が強かったので、ついには息を切らしてこう言いました。「お前や! 本当にもっと細い鉛筆を手に入れにゃならんよ。余にはこいつがちっともうまく扱えん。書くつもりのないことばかり書いてしまう――」
「どのようなことを?」クイーンはそう言って備忘録をのぞきました(アリスはこう書きこんでいました。『白のナイトが 火かきぼうを すべりおっこちてる バランスをとるのが すごくへただ』)。「これはあなたの気持ちを書き留めたものではありませんわね」
テーブルの上のすぐそばにご本が一冊置いてあったので、アリスは椅子に座って白のキングを見守りながら(まだちょっとキングのことが心配だったんです。また気を失ったらすぐにインクをかけてあげられるように準備もしていました)、自分にも読めるところはないかとページをめくりました。「――全部知らない言葉で書かれてるんだもの」アリスは心の中でつぶやきました。
こんな具合だったんです。
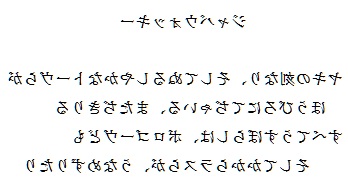
読めそうにも見えるので、アリスはしばらく頭をひねっていましたが、ようやくのことでパッと思いつきました。「なんだ、もちろん鏡のご本なのよ! だから鏡にかざせば、言葉はみんなまたちゃんとした向きになるわ」
これがアリスの読んだ詩です。
ジャバウォッキー
|
ヤキの刻なり、そしてぬるしやかなトーヴらが ほうびろにてぢゃいる、またぢきりる すべてうすぼらしは、ボロゴーヴども そしてかからラスらが、うなめずりたり
「ジャバウォックに用心せよ、我が息子よ! 咬みつく ジャブジャブ鳥に用心せよ、そして避けよ いらだくるうバンダスナッチを!」
彼は そしてタムタムの しばし立ち、思いにふける
そして、さかなぶる思いで彼の立ちたりし時 かのジャバウォック、炎の両の ふくらかき森を抜け、ひょうとなりて現れる そして迫りつつ、あわだくる!
一刀、二刀! 一刀、二刀! そして貫きて貫き かのことしえの 彼は 彼はいっきようようと帰りゆく
「では汝はジャバウォックを討ち取りしか? 我が 嗚呼、こうこうたる日じゃ! らっぱれや! らっぱれ!」 彼は己が喜びにわらばなつ
ヤキの刻なり、そしてぬるしやかなトーヴらが ほうびろにてぢゃいる、またぢきりる すべてうすぼらしは、ボロゴーヴども そしてかからラスらが、うなめずりたり |
「とてもすてきな感じね」アリスは読み終えると言いました。「でも、ちょっと分かりにくいな!」(なにしろ自分自身にさえ、ちっとも分からないとは打ち明けたくなかったんです)「なんだか、いろんなイメージで頭がいっぱいになるみたい――ただ、それが何かはよく分からないけど! でも、誰かが何かを殺した。とにかくそれははっきりしてるわ――」
「でも、あ!」突然アリスは立ち上がりました。「急がないと、このおうちのほかのとこがどんなふうか見ないうちに、鏡を通って戻んなくちゃいけなくなっちゃう! まず、お庭を見てみよう!」アリスはすぐにお部屋を出て、階段を駆けおりました――と言うか、正確には駆けたんじゃなくて、速く楽に階段をおりる新発明の方法(とアリスが思ったんです)でおりました。指先を手すりに添えていただけで、足は階段に触れもせずにふわーっと舞いおりたんです。そして浮いたまますうーっと広間を通り抜け、もしも戸口の柱をつかまなかったら、そのまままっすぐドアから出ていってしまったでしょう。アリスはあんまり宙に浮いていたせいでちょっとクラクラしてきていたので、気がつくと元のように普通に歩いていたことに、むしろホッとしました。